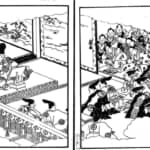「道長無双」の象徴となった後一条天皇
紫式部と藤原道長をめぐる人々㊺
■在位中の政治は彰子や頼通によって安定した
後一条(ごいちじょう)天皇は、一条天皇の第二皇子として1008(寛弘5)年に誕生した。母は藤原道長の長女である藤原彰子(あきこ/しょうし)。三条天皇の皇太子となったのは1011(寛弘8)年で、天皇に即位したのはわずか8歳の時だった。
まだ幼い天皇を支えるべく、後一条天皇にとって祖父であり、時の左大臣である道長が摂政を兼任。道長は翌年には辞任し、長男の藤原頼通(よりみち)に摂政を譲っている。
後一条天皇に譲位するにあたり、三条天皇は自身の第一皇子である敦明(あつあきら)親王を次の皇太子に立てることを条件とした。この希望は叶えられたものの、道長は皇太子に継承されるはずの壺切御剣(つぼきりのみつるぎ/つぼきりのぎょけん)を敦明に渡さなかったり、皇太子の身の回りの事務を行なう東宮大夫の人事に無関心を装ったりするなど、ことあるごとに協力を拒んだ。
露骨な嫌がらせにもかかわらず、敦明親王に対する支援を申し出る者がほとんどいなかったのは、絶対的な権力者である道長の顔色をうかがったからだろう。
後ろ盾となるはずだった父の三条天皇が崩御したこともあり、将来を悲観した敦明親王は、わずか半年ほどで皇太子を辞退。同じく道長の孫で、後一条天皇の弟である敦良(あつなが)親王が次の皇太子に選ばれたのは、道長の思惑通りに事が運んだ結果といえる。
■威子が入内し「一家三后」が実現
後一条天皇は1018(寛仁2)年に元服。通常の元服より急いだのは入内を早めるためといわれており、父の一条天皇の際も同様のことが行なわれている。
後一条天皇に入内したのは、道長の三女である藤原威子(たけこ/いし)だった。天皇の后を道長の血縁で独占するための政策であり、長女・彰子(一条天皇中宮)、二女・藤原妍子(きよこ/けんし/三条天皇中宮)がそれぞれ太皇太后、皇太后となった上、威子が中宮となったため、道長の栄華は頂点に達した。前代未聞の出来事に、公卿の藤原実資は「一家立三后、未曾有」(『小右記』)と驚きを隠さなかった。
後一条天皇に入内した威子は、天皇の8歳年上。劇中ではことさら年齢差を気にする威子の様子が描かれたが、実際の二人は、小柄で美しい威子に対し、後一条天皇も早熟でたくましく成長しており、お似合いの二人だったらしい(『栄花物語』)。
威子が後一条天皇にとって唯一の后となったのは、二人が仲睦まじかったから、というわけではなさそうだ。道長を祖とする御堂流以外に外戚の地位を奪われないようにするため、との策略があったらしい。
しかし、二人の間に生まれたのは、女児2人。男児が生まれることはなかった。つまり、後一条天皇に直接つながる系統は、ここで途絶えることとなった。
後一条天皇の在位は20年におよんだが、積極的に政治に携わることは少なかったらしい。政務を取り仕切ったのはほとんど彰子や頼通らだったといわれている。
1036(長元9)年に、28歳で崩御。后の威子も、約半年後に疱瘡(ほうそう)を患い、後を追うように死去した。
後一条天皇と威子の間に生まれた2人の皇女である章子(しょうし/あきこ)内親王と馨子(けいし/かおるこ)内親王はそれぞれ天皇に入内しているが、章子内親王に子はなく、馨子内親王の生んだ皇子と皇女は早逝している。天皇よりも力を持つようになった藤原氏による摂関政治は、いよいよ終焉を迎えようとしていたのである。
- 1
- 2